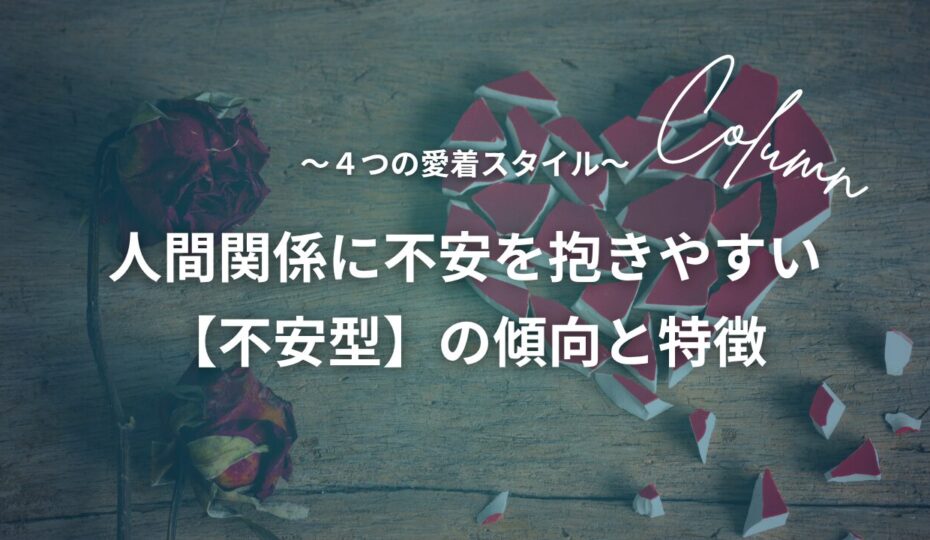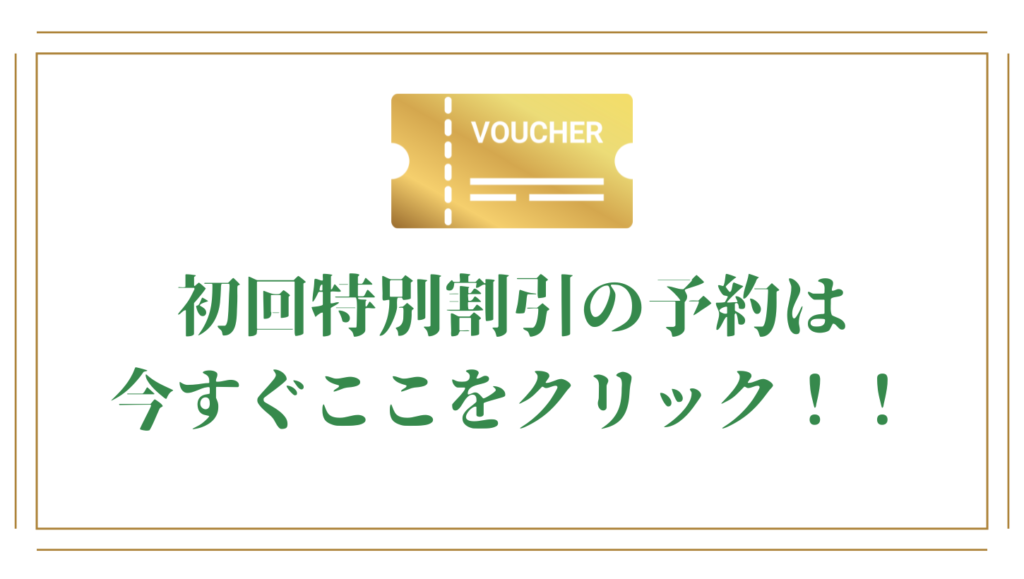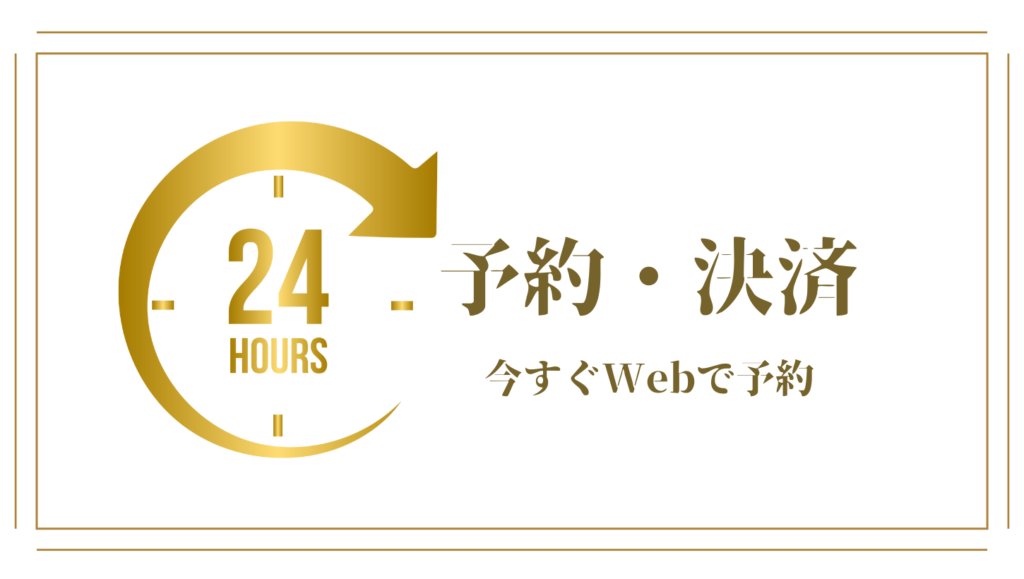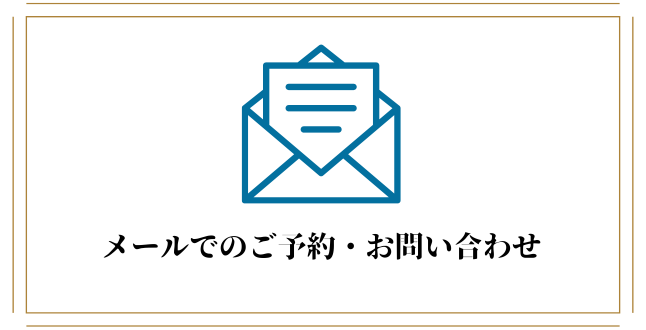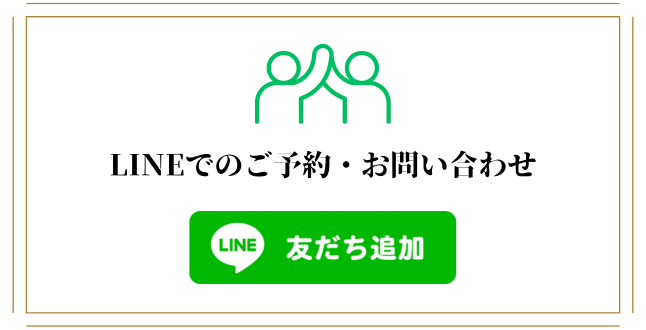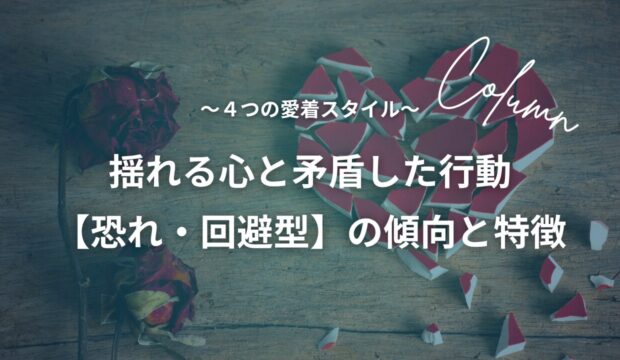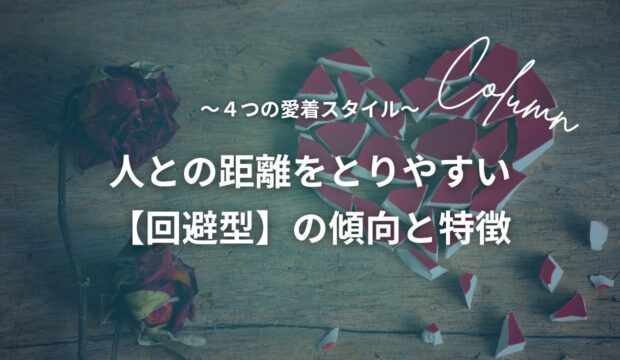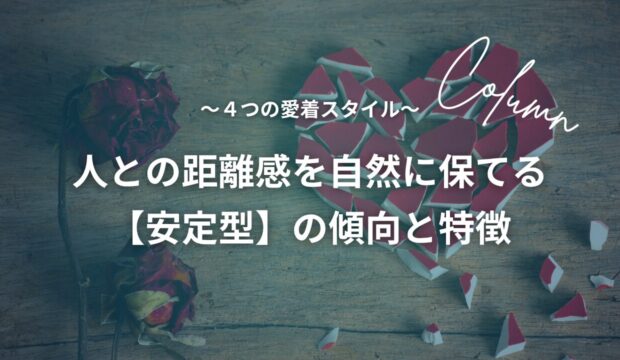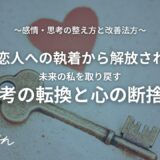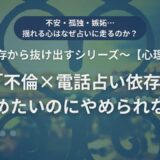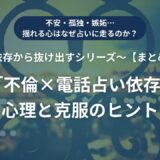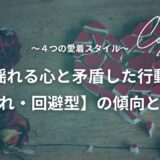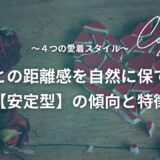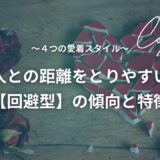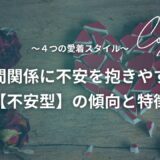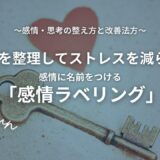愛着スタイルは大きく4つのタイプに分類されます。
幼少期の親子関係や育った環境の影響により、人との「つながり方」や「距離のとり方」に無意識の傾向が現れるといわれています。
- 🔹 安定型(Secure) … 自分にも他人にも信頼を持ちやすいタイプ
- 🔹 不安型(Anxious) … 愛されることに強い不安や執着を抱きやすいタイプ
- 🔹 回避型(Avoidant) … 親密さを避け、相手との距離を保つことで自分を守ろうとするタイプ
- 🔹 恐れ回避型(Fearful-Avoidant) … 愛情を求めながらも傷つくことを恐れ、近づいたり離れたりを繰り返しやすいタイプ
▼ 目次
人間関係に不安を抱きやすい不安型の傾向と特徴
―― 相手の気持ちに過敏に反応し、不安が強くなりやすいタイプ
不安型愛着スタイル(Anxious Attachment)は、人との関係において強い不安感や見捨てられ不安を抱きやすい傾向がある愛着スタイルのひとつです。恋愛やパートナーシップの場面では、相手の言動に一喜一憂し、強い執着や依存的な態度が表れやすくなります。
本人がこのスタイルを持っているケースもあれば、パートナーが不安型傾向を示す場合もあり、いずれにしても人間関係において“距離感”のコントロールが難しくなりやすいのが特徴です。
不安型の特徴と行動パターン
- 相手からの連絡が少しでも遅れると、強い不安を感じる
- 「嫌われたのではないか」「見捨てられるのではないか」という思考がよく出てくる
- 相手に「必要とされたい」「役に立ちたい」と強く望み、過剰に尽くす
- 自己肯定感が低く、「自分には愛される価値がない」と感じやすい
- 相手の態度が少しでも変わると、敏感に反応し振り回されやすい
- 感情を抑えすぎて爆発することがある
これらの特徴は、パートナーとの関係の中で繰り返し表れることが多く、一見“依存的”とも見える行動が背景にある不安感から来ていることも少なくありません。
形成される背景
不安型愛着スタイルは、幼少期の家庭環境や親との関係性によって形成されることが多いとされています。たとえば以下のような体験が背景にあることがあります:
- 親の関心や愛情が一貫していなかった
- 「いい子でいないと愛されない」と感じながら育った
- 親が過干渉だったり躾が厳しかった
- 親が常に心配しすぎて子どもにも不安を伝えていた
- 感情を自由に表現できる環境ではなかった
- 親の気分や機嫌によって対応が変わり、安心できなかった
このような環境で育つと、「人とのつながり=不安定なもの」「愛は条件付きでしか得られない」といった認識が無意識に根づき、大人になってからの人間関係でも、相手の反応に過敏に反応しやすくなると考えられます。
恋愛におけるパターン
恋愛関係において、不安型の人は相手との距離が離れることを非常に恐れます。 つながりを求める気持ちが強い一方で、拒絶されることへの恐れから、自分の思いを飲み込んでしまうことも少なくありません。
関係が少しでも不安定に感じられると、「嫌われたかもしれない」「捨てられるかも」といった思考が頭をよぎり、その不安を振り払おうとして、相手に確認や執着的な行動をとってしまうケースも見られます。
恋愛で見られる主な行動例:
- 相手の言動を常に気にして疲弊してしまう
- 相手に合わせすぎて自己を見失いやすい
- 相手の愛情を試すような行動に出てしまう(無視・泣き落とし・束縛など)
- 我慢し続けた結果、自爆的に関係を壊してしまう
こうした行動は、愛されたい・安心したいという強い願いの裏返しであり、その人が本来“情の深い人”であることの証でもあります。
補足:不安型と回避型の関係について
カウンセリング現場では、不安型と回避型という異なる愛着スタイルを持つ二人が、強く惹かれ合い、そしてすれ違いやすくなるというケースが非常に多く見られます。
この関係は、恋愛依存・共依存・回避依存といった視点からも理解されることがあり、一見すると真逆の性質を持つ二人が、実は深い共通点を持っていることも少なくありません。
この構造については、今後「コラム」にて詳しく解説する予定です。
自分が不安型の場合に役立つこと
不安型の傾向がある場合、まずは「自分が不安を感じやすい傾向にある」ことに気づくことが第一歩です。そのうえで、以下のような視点や行動が、感情の波に飲み込まれずに自分を保つ助けとなります。
- 相手の反応に一喜一憂する前に、自分の感情に注目する
- 不安になったとき、自動的に行動せず、一度立ち止まる習慣をつける
- 「断る・頼る・甘える」など、自己肯定感を育てる小さな経験を積む
- 共感的な人間関係の中で、自分の心の安全基地を築いていく
言葉による安心のやりとりができる関係性を持つことも大切です。たとえば「何が不安だったのか」「どんなふうに感じたのか」「どうしてほしかったのか」などを言葉にすることで、相手との間に安心と理解が生まれやすくなります。
パートナーが不安型の場合は?
相手が不安型の傾向を持っている場合、「なぜそんなに不安になるのか分からない」と感じてしまうこともあるかもしれません。しかし、不安型の人は、相手を困らせたいのではなく、安心したい・大切にされていると実感したいという気持ちを強く抱えています。
そのため、以下のような対応が関係を安定させる助けになります:
- 安心できる言葉を、できるだけ明確に伝える(例:「大丈夫だよ」「ちゃんと考えてるよ」)
- 予測可能な対応を心がける(気まぐれな言動は不安を強めやすい)
- 「それは心配になるよね」と感情を否定せずに受け止める
- 一時的な距離が必要なときも、「離れるけど気持ちはある」と言葉で補う
不安型の人と関わるときは、「気持ちを安定させてあげなければ」と抱え込むのではなく、安心を分かち合う“チーム”として向き合うことが大切です。
まとめ
不安型愛着スタイルは、「つながりを失いたくない」という強い願いがある一方で、
相手のちょっとした反応に傷つきやすく、自分でも理由がわからないまま不安が高まってしまう――そんな“こころの揺れ”を抱えやすい傾向があります。
けれども、これは弱さではありません。豊かな感受性と情の深さがあるからこそ感じる痛みであり、
安心できる関係性や適切なサポートがあれば、「不安はシグナル」「つながりは育てるもの」へと視点を変えていくことが可能です。
もし今、
「頭ではわかっているのに気持ちが追いつかない」
「距離の取り方がわからず毎日がしんどい」
――そんな思いで立ち止まっているなら、ひとりで抱え込まず専門家に話してみませんか?
『Megimi/めぎみ』 のカウンセリングでは
- あなたを否定せず、今感じている不安をそのまま受け止める
- 感情の仕組みと愛着スタイルを“言語化”しながら一緒に整理する
- 毎日の行動が少しずつ楽になる、具体的なセルフケアやコミュニケーション方法を提案する
「今の苦しさを手放し、安心できるつながりを築き直したい」――
そう感じたタイミングが、変わり始める最適なタイミングです。
あなたのペースで大丈夫。一歩踏み出すときは、いつでもお待ちしています。
👑ご予約・お問い合わせはこちらから
苦しさや迷いを抱えながら、 ひとりで頑張ってきたあなたへ。 今こそ、その一歩を踏み出すときです。